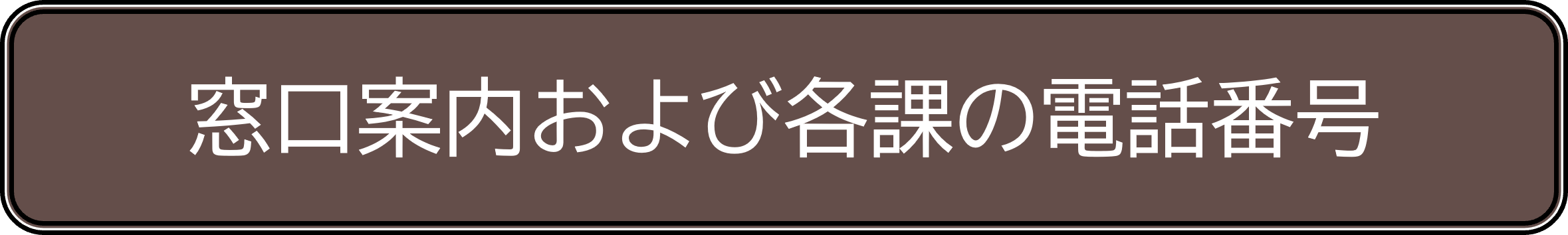療養費の支給
1.療養費
次のような場合に、医療費の全額を負担したときは、申請して認められれば、保険給付分が支給されます。- 医師が必要と認めたコルセットや9歳未満の小児弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(以下「小児弱視等」という)の治療用眼鏡、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣などの治療用装具。
- 急病などで、保険証を医療機関等に提示できず診療を受けた場合。
手続きに必要なもの
1. 必ず必要な書類
-
 国民健康保険療養費支給申請書(pdf 99 KB)
国民健康保険療養費支給申請書(pdf 99 KB)
※ 書き方については、こちら(pdf 297 KB)
書き方については、こちら(pdf 297 KB)
- 保険証
- 領収書
- 世帯主の振り込み口座が確認できるもの
※振り込み口座を世帯主以外の方にする場合は、世帯主からの![]() 委任状(pdf 20 KB)が必要となります。また、振り込み口座が確認できるものが必要となります。
委任状(pdf 20 KB)が必要となります。また、振り込み口座が確認できるものが必要となります。
2. 上記のものに加えて必要な書類
- 治療用装具のコルセットの場合
医師の証明書 - 小児弱視等の場合
作成指示書 - 弾性着衣などの治療用装具の場合
弾性着衣等の装着指示書 - 保険証を医療機関等に提示できず自己負担した場合
診療報酬明細書
これらを持参の上、住民生活課または、各支所の窓口まで手続きしてください。
2.柔道整復師等の施術
保険を使えるのはどんなとき
- 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
- なお、骨折及び脱臼については
応急手当の場合は、医師の同意は必要ではありませんが、応急手当後に引き続き治療するためには、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療を受けるときの注意
- 単なる肩こり、筋肉疲労などへの施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、申請書の受取代理人欄に原則患者の方の自筆による記入が必要となります。
- 保険医療機関(病院・診療所など)において同一疾病の治療を受けている場合、重複する期間の柔道整復師(整骨院・接骨院など)の施術については健康保険の給付は受けられません。
- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
- 外傷性の負傷ではない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は健康保険の給付は受けられません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険者に連絡してください。
柔道整復師の療養費と他の療養費との違い
- 療養費は、本来患者の方が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復師については、例外的な取り扱いとして、患者の方が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者の方に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
3.あん摩・マッサージの施術
保険を使えるのはどんなとき
- 筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症状(制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とするもの)の施術を受けた場合に保険の対象となります。
治療を受けるときの注意
- マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
- 定期的(3か月ごと)に医師の同意が必要となります。
※変形徒手矯正術は1か月ごとに医師の同意が必要です。
4.はり・きゅうの施術
保険を使えるのはどんなとき
- 主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けた場合に保険の対象となります。
治療を受けるときの注意
- 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
- 保険医療機関(病院・診療所など)において同一疾病の治療を受けている場合、重複する期間のはり・きゅうの施術のついては健康保険の給付は受けられません。
- 定期的(3か月ごと)に医師の同意が必要となります。
【関連資料】
掲載日 令和6年11月7日
更新日 令和7年2月20日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 医療保険係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6909